

妊娠・出産からの育児……仕事との両立は難しいの?

人生の中で大きなライフイベントの一つでもある妊娠・出産・育児。今でこそ制度は整ってきていますが、それを使いこなすのは一苦労です。十月十日お腹の中で育て、現代の進歩した医学の中でも苦しい時間に耐え、やっと出会えた我が子を抱いた瞬間から次には、授乳や夜泣きなどの育児が待っています。
妊娠・出産・育児の問題になると必ず直面するのが仕事との両立。昔は男性が働き、女性が家を守り育児を問う役割で成り立っていましたが現代ではそうもいきません。共働きが当たり前とされる世間の流れと同様に、女性自身の働いてキャリアを築きたい気持ちも高まっています。
しかしそんなに簡単に体は回復せず、妊娠・出産・育児に対する代わりは誰もおらず、キャリアを諦めるという人も。妊娠・出産からの育児…仕事と両立するには、どのようなことを大切にすればよいのでしょうか。
仕事と育児の両立には周囲の協力が不可欠

妊娠・出産・育児は新しいことばかりわからないことばかりで新鮮な反面、体力や精神面での負担、金銭的負担も少なくありません。とくに仕事との両立においては、周囲からの協力は必要不可欠。「お母さんなんだから」「こんなことみんなやっているんだから」と、一人で抱え込む人も多いですが、会社での働き方サポート、地域や住環境の中でのサポート、保育園など、周囲の協力が大切です。
子どもの発熱、トラブルなどは予測不可能。仕事のように慣れることは一生ないといえます。そして仕事と違い、子どもにとって親の代わりはいません。
自分一人でやろうとするのではなく、今の自分の状態、家庭の金銭面での状況や夫・実家などのサポート体制、区や住んでいる場所での保育園や子育て支援の条件など、使えるものをフル活用することも、仕事と子育てを両立するための一歩です。
妊娠がわかったら考えておきたいこと

妊娠がわかることが突然だった、という声は少なくありません。妊娠がわかれば、自分の体調に波があるだけではなく、動きなどにも制限が出てきます。安定期に入るまでの期間は周りにも言わずにいる人も多く、体調と周りへの配慮に葛藤してしまうこともあるでしょう。ここでは、妊娠がわかったら考えておきたいことをご紹介します。
パートナーとの役割分担
子どもを一人で育てるのは負担が大きいもの。大人二人が各々のことができる状態での同棲や結婚生活と違い、手取り足取りしなければ命に関わる小さな生命を抱えての生活です。
女性は仕事をセーブしたり、普段できていたこともできなくなったりすることも少なくありません。妊娠中や出産後の家事や育児の役割分担や、育休の取得時期などしっかり話し合っておきましょう。
妊娠中の働き方や産後の職場復帰
妊娠中のつわりやマイナートラブルは、人によって程度が異なるもの。なかにはつわりがひどく、入院や通院をしたり、点滴が必要だったり、辞めざるを得ないという人もいます。
妊娠中の働き方や産後の職場復帰について、自分自身の願いや考えをまとめ、パートナーとも共有しておきましょう。気持ちの問題と実際に体に起こる変化は別物です。
職場への報告タイミング
職場への報告のタイミングも考えておきましょう。「いますぐにでも!」と気持ちが高まってしまいがちですが、トラブルなどを含め、少し安定してからのほうがよいとされています。
また多くの人が安定期に入ってから報告しますが、実際に多いのは2ヶ月から3ヶ月程度の頃。引き継ぎやお腹の大きさなどを考慮する場合が多いとされています。
職場へ報告するときに話しておきたい内容
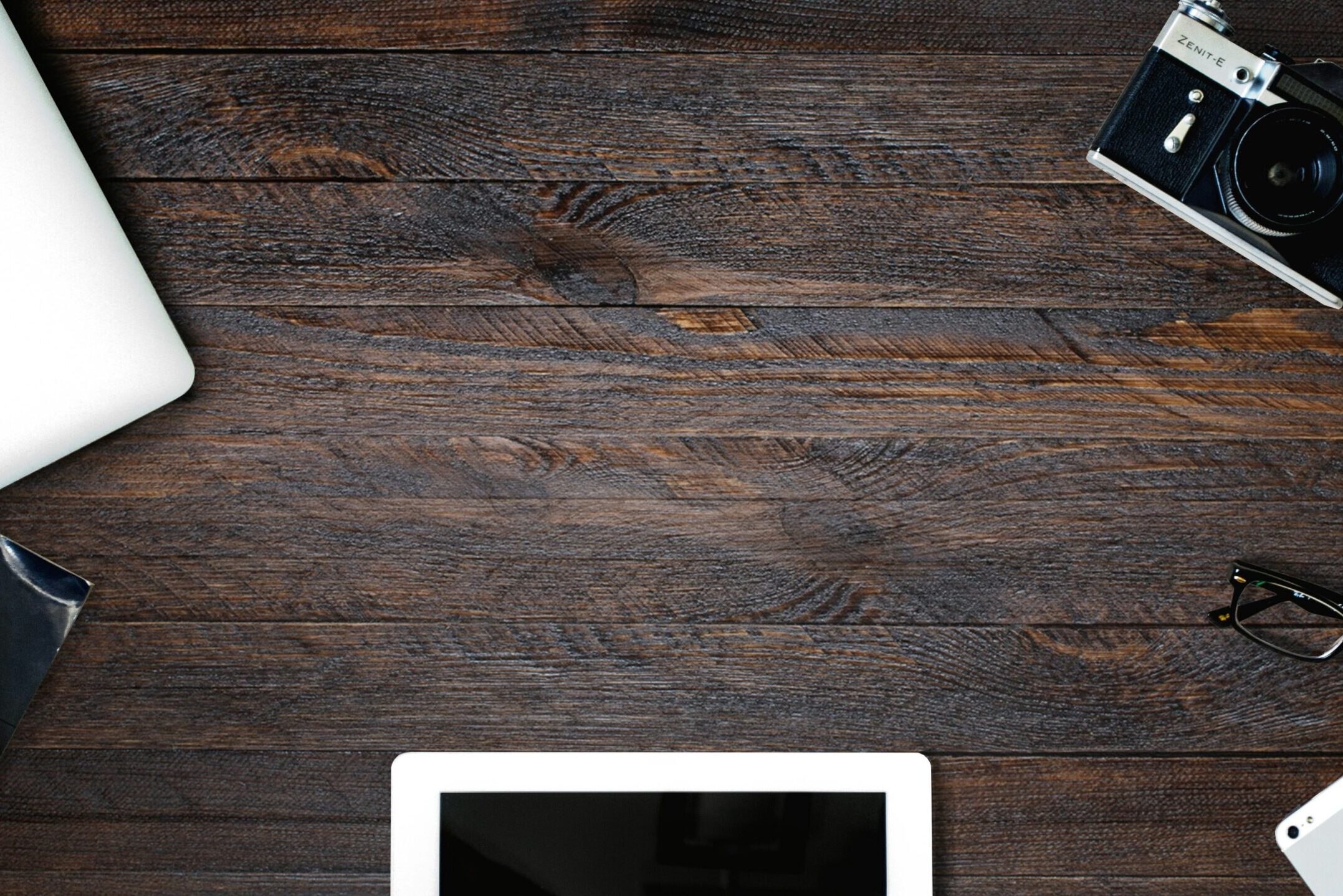
妊娠検査薬などを使って妊娠がわかった後、病院での妊婦健診で確定したら早めに職場に報告しておく必要があります。職種にもよりますが、体力面などでの負担が大きくかかる場合、セーブするためには周りの理解や協力が必要です。しかし、その一方で配慮も求められます。ここでは、職場へ報告するときに話しておきたい内容をまとめてご紹介します。
1. 妊娠したことの報告と安定期の目安時期
職場に報告するのは、安定に入る少し前の人が多いといわれています。妊娠したことの報告と安定期の目安時期を医者の診断のもと、伝えるようにしましょう。
会社によっては、それよりも早い時期から産休・育休に入れるよう手続きをしてくれたり、マイナートラブルの対策をとってくれたりすることがあります。また、書類関係の申請にも必要な情報となることが多いでしょう。
2. 今後の業務や働き方
妊娠したら産休に入るまでの業務や働き方について相談しましょう。妊娠するとこれまで通りの仕事量や責任を負うのが難しくなることも少なくありません。つわりで体調が悪い日が続けば、欠勤や出勤時間の変更なども生じるでしょう。
あらかじめ今後の業務や働き方について相談しておけば、安心して妊娠中も仕事に励めるでしょう。
3. 現在の体調や配慮してほしい点

妊娠初期の症状はさまざまです。つわりがまったくない人もいれば、食べづわり、吐きづわりと、心身的にきつい人も一定数います。現在のつわりや体調の状態、配慮してほしい部分などを簡単にでも伝えておきましょう。「今のところつわりはないが、今後あるかも」と可能性も一緒に伝えておくのがポイント。
なるべく快適に職場で過ごすためにも、苦手なニオイや場所を共有しておくと安心です。仕事内容によりますが、チームや何人かで動いている場合は周知してもらうことで自分の負担が軽くなりますよ。
4. 出産後の復職意志の有無
配慮の点や今後の働き方を話すときに、あわせて復帰の意思や復帰後の働き方なども相談しておきましょう。時短勤務や保育園などのサポート、会社としてのサポート体制などもしっかりと話し合っておくことが今後の関係や働き方、仕事との両立に大切なポイントです。
会社によっては、ママさんがいないあるいは産休から取る人が初めてなどの場合もあります。このような場合は会社側も手続きや対応に不慣れな部分があるので、ゆっくり着実に進めていきましょう。
妊娠中も仕事を続けられるとは限らない

念願叶った職場や、職種、やりたかったことをできる環境になってきた頃に妊娠が発覚。思いがけない妊娠だけど、できればここで働き続けたいと思う人も少なくないでしょう。
しかし、妊娠中の体調は妊婦自身も予測できないものばかりです。つわりの有無、種類、自分でも陥ったことのない感覚や体調不良に悩まされることも少なくありません。
さまざまな働き方が推奨されている現代ですが、働くよりも体を休めなければいけないこともあるでしょう。今が平気でも今後の体調や自分の負担次第で、働き方を検討するタイミングがあるかもしれないことを念頭に置いておきましょう。
出産後の働き方はどうする?考えるときのポイント

無事に産休を経て、仕事をしたいと思ってもスムーズに復職できる・仕事ができる人は多くありません。たとえば1年という短い間であったとしても、社会の仕組みや、会社の制度、自身の体調などさまざまな変化が起きるものです。出産後の働き方をどうするのか、考えるときのポイントをご紹介します。
1. 今後も同じ会社で働き続けるか
会社での制度が整っているのであれば、その職場で働き続けたいと願うのは当然です。しかし、会社によっては時短勤務が難しい場合や、産休明けのママにとっては厳しい環境や状況の場合もあります。
今の仕事内容を復帰した後に同じだっけの量をこなせるのか、給与形態やパートナーとの金銭部分での負担などを加味して、考えたり家族や上司と話し合ったりしておきましょう。
2. 親族やパートナーのサポート体制はどうか
復帰したいと願っても親族やパートナーのサポート体制が整っていない場合、復帰自体が難しい場合も。パートナーの仕事状況や周りに頼れる人がいるか、区や市などのサポート体制を受けられるかどうか事前に調べておきましょう。
産後に限らず、今後育児をしていくうえでパートナーや親族のサポート体制がない場合、ワンオペ状態で子どもと向き合うことになります。自身の負担を軽減するためにも、周りのサポート体制を整えておきましょう。
▼あわせて読みたい!共働きで子育てをやっていくコツとは?無理せず育児を楽しむアイデア集

3. 保育園の預け先は決められそうか

保育園や幼稚園、保育所などの預け先が決められるかどうかは、産後の働き方の大きなポイントとなります。
2025年現在、保育園はいまだに待機児童がいるといわれているほど。地域によっては激戦のまま、数年入れない人も少なくありません。2025年を境に児童数の減少により運営の継続が困難となる保育所が増えるおそれがある「2025年保育園問題」もあるため、早めに保育園に入園できるか調べておくことが大切です。
4. フルタイム勤務か時短勤務か
会社によって制度が異なりますが、フルタイムか時短勤務が可能かを確認しておきましょう。保育園などは預けられる時間が決まっており「何時までに迎えにきてください」「延長保育は何時までです」と規則があります。
フルタイムの方が給与が高いことは周知の事実ですが、時短勤務でなければ保育園のお迎えに間に合わないこともありますよね。起こりうる問題や葛藤をしっかりとパートナーと話し合って、勤務スタイルを決めましょう。
5. 職場のサポート体制は充実しているか
会社によっては、産後や育休明けのサポート体制が万全で「ママ・パパに優しい会社」として知られているところもあります。また会社内に保育所があったり、子ども関係の病院と連携しているところも少なくありません。
時短勤務の体制などを含め、職場のサポートがしっかりしているか確認しましょう。また制度としてはあるものの機能していない場合もあるため、きちんと対応を伺うことをおすすめします。
出産後も自分らしく働くために大切なこと

女性にとって出産は人生の中でも大きなイベント。体も心も今までのようにはいかなくなることも多くなります。そのような状態で出産後も自分らしく働くためには、どのようなことを大切にすればよいのでしょうか。
1. 周囲のサポートを積極的に頼る
産後の疲れやホルモンバランスの乱れも相まって、周囲に頼らず一人でこの子を守らなければと思ってしまったり、家事や育児を完璧にできないことに落ち込んでしまったりすることもあるでしょう。
しかし、仕事と育児、家事を両立するのに周りの協力は不可欠です。保育所や市区町村のサービス、実家や義実家、親戚や近所の友人など、サポート体制が充実しているなら、積極的に頼って自分の負担を減らしていくことを考えましょう。
また家事代行・ベビーシッターなどは、住んでいる地域によっては定額や無料で受けられる場合があります。
2. パートナーと協力し合う
パートナーと協力し合うことは、最も重要なことです。育児や家事をはじめ、子どもの保育園や習い事の送迎なども協力し合いましょう。
「早く帰宅したほうがご飯を作る」「〇曜日は〇〇が送迎する」など、あらかじめ話し合っておくと、仕事復帰後の負担が軽減します。また、保育園からのお迎え要請や病気で預け先がないときの対応についても話し合っておくことも重要です。
3. 完璧にこだわらない

マルチタスクが得意な女性は、完璧にタスクを終わらせたいと考える人が多い傾向にあります。しかし、産後の疲れやホルモンバランスの乱れもあるので、妊娠前のパフォーマンスに戻るには時間がかかるもの。
どんなに完璧な家事をして、仕事をして、周りから評価を受けていたとしても、出産をした後も同じようにできるわけではありません。完璧にこだわらず、自分のペースで、一つひとつに向き合いましょう。
4. 昇進やキャリアアップを焦らない
昇給やキャリアアップは、焦ることでどんどん自分を追い立ててしまい焦燥感で周りとの関係やパートナーとの関係も悪化してしまいがちです。なかには「子どもを産んだせいで」と、矛先が変わってしまうケースも少なくありません。
復帰後はまず、新しいスタイルに慣れるところから始めましょう。段階を踏むうちに昇進やキャリアアップのチャンスが舞い込むはずです。それまでは目の前のことに集中し、成果を出していきましょう。
5. 自分だけの時間を確保する
出産後、優先順位は子どもになっていくのは自然なこと。「自分の時間を持つなんて罪悪感がある」と思う人もいるかもしれませんが、決して悪いことではありません。
自分だけの時間を確保することは、子どもと向き合ったり自分自身をしっかり整えたりするために必要なことです。
カフェで本を読む、ウィンドーショッピングに足を運ぶ、美容院に行くなどなんでもよし。時間が許す限り、好きなことをして過ごしましょう。
ライフスタイルが大きく変化するイベント「出産」

人生の中で、男女共に大きなイベントとなる出産。とくに女性にとっては、自分の命をかけたものであり、大きな変化を余儀なくされるものでもあります。今まで経験したことのない出来事、感情、体調や体型の変化にも戸惑い、自分自身でも追いつかないまま社会復帰や働きの場に戻るという人も少なくありません。
仕事は大切です。しかし、それよりももっと生まれたばかりの我が子との時間や、その我が子と向き合うための自分の時間、そして周りとの連携・協力が必要となってくるでしょう。
同棲や結婚とは違い、ライフスタイルが大きく変化するイベントだからこそ、自分一人で抱えるのではなく「辛い」「きつい」を伝え、今の自分の状態と仕事とのバランスを夫婦や職場の仲間たちとどのように考えていくかが重要です。