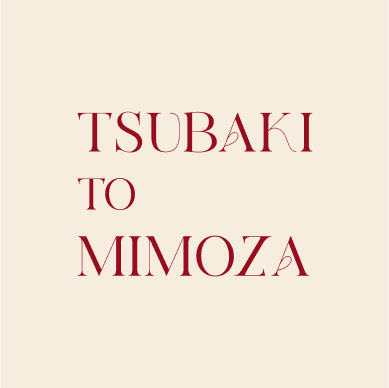“推し”という、存在

赤坂アカ氏と横槍メンゴ氏は、『推しの子』という漫画を描いた。
宇佐見りん氏は、『推し、燃ゆ』という小説を書き、「推しは背骨である」と言った。
今、多くの作品の題材となる“推し”という存在。
何かを推すことで、生き甲斐を見い出すことができる。
または、一種のアイデンティティ、自己表現なのかもしれない。
推しに会えるから、それまで頑張ることができたり─。推しが笑っているから、今日も笑うことができたり─。
そんな存在が自分の人生に在ることで「幸せだ」と思えるのは、とても幸せなことであり、そして不自由なことでもあると思った。
縋ること。依存すること。
悲しいことがあったときに、縋るものや、依存できる場所があることで、救われることがあるのも事実で。
私にとって、それは小説だった。
小さい頃から、耐え難い苦痛を感じた時や、感情のコントロールができずに心の中から溢れ出す混沌とした何かを吐き出したい時は、小説の中の世界に逃げ込んだ。
小説と私との間には、0.1ミリも隙間が存在しなかった。
私の人生は、小説に逃げ込むことで救われてきた。
中でも、とにかく暗い作品を選んできた。
焦燥感、恐怖、絶望、嫌悪、憎悪。そんな感情をもたらす小説に縋ってきた。
縋ることで、救われた。縋らなければ、救われなかった。
現実世界の生きづらさに葛藤する私と、それ以上に苦しい体験を繰り返す小説の中の架空の人物。その架空の人物の気持ちに寄り添っている時だけは、「私はまだ大丈夫だ。」「私は幸せだ。」と思えた。だから、暗い作品を好んできたのだろう。
小説がなければ生きることさえ難しかったのではないか?と思ったこともあった。
小説が、全てから救い出してくれていた。逃げ場を作ってくれていた。
私にとっては、保健室みたいな存在なのだと思う。

縋ることで、生きられたから。
私は昔から、音に敏感だった。
雨が窓をカタカタと打つ、不快な音。外を走る車のエンジン音には、威圧感を感じた。飲食店で聞こえてくる人々の声は、ザワザワとした音として聞こえるのではなく、会話という形として聞き取ることができてしまった。
だから、耳を使うことが苦手だった。そして、触覚や嗅覚にも好き嫌いが多かった。そして、脳死して何かを視聴することも大の苦手だった。
小説は、想像できるから好きだ。
作者が何を伝えようとしているのか─。何も伝えようとはしていないのか─。
そんなことを考えながら、情景を頭に浮かび上がらせ、私の世界と作者の世界が融合し作り上げられていく世界に浸ることで、「生きていてよかった。」と思える。
時には、文章から光が放射しているのではないかと思うほど、言葉がキラキラと光って見えた。
時には、たった一文に涙した。涙腺が自分の意識とは違う場所にあるかのように、自分の体ではないかのように溢れて止まらなかった。
周囲の音が聞こえなくなるほど没頭すると、この世界に自分だけが残された気がして嬉しくなったりもした。
小説を読み終えた後は、いつも冷静に自分の人生を見つめ直すことができた。
自分にとって何が大切で、何を求めているのか、考えたいと思えた。
胸の真ん中に大きく居座っていたストレスや悲しみ、空虚や不安は、すーっと消えていた。
そして、また新たな小説(逃げ場)を探した。
無意識に縋っていたい。
無意識に「なぜ、縋らないと生きていけないのか?」「なぜ、推しがいる(ある)ことで幸せだと思えるのか?」と、考えることから逃げていた。
でも、気づかない方が、幸せのように思う。
ただ、好きだから─。ただ、愛おしいから─。ただ、救われるから─。ただ、生き甲斐だと思えるから─。
そんな理由で、いい。そんな理由が、いい。
ただでさえ、毎日のように考え、悩み、決断を繰り返さなければ生きていくことができないのが人間なのだから、何かを無性に必要とすることで、“本能”を思い出せたらいい。
「推しが居なくなったら、どうしよう…。」
そんな不安に苛まれる不自由さも、愛するものがなければ生まれない。
ひたすらに愛しているからこそ生まれてくる感情全て、“本能的”で愛おしく思う。
そんな不自由を求めていたっていい。